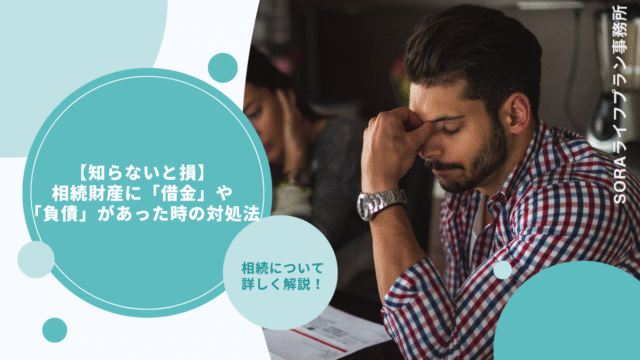急に相続が発生!「預金や金融資産」を確かめる方法と手続きをFPが解説
家族が急に亡くなり相続が発生すると、まず困るのが「故人(被相続人)がどの銀行にどれくらいの預金を持っていたか?」という問題です。通帳が見つからず、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
この記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)が、預金口座の調べ方から、銀行での解約・名義変更手続きまでを、4つのステップで具体的に解説します。この記事を読めば、迷うことなくスムーズに手続きを進めることができると思います。
親の預金口座が分からない時の調べ方(通帳がない場合)
故人の遺品整理をしても通帳やキャッシュカードが見つからない場合、金融資産の全体像を把握するために、以下の方法で調査を進めましょう。
ステップ① 自宅内と郵便物を徹底的に調べる
まずは基本的な調査です。
遺品整理: 故人の机や書斎、引き出し、カバンや財布の中、仏壇の近くなどもをくまなく探します。
郵便物: 過去1年程度の郵便物をチェックします。「定期預金の満期案内」「取引残高報告書」「配当金の通知」「クレジットカードの引き落とし履歴」など、金融機関との取引を示す手がかりがないか探します。
ステップ② 銀行に「残高証明書」を請求する
もし銀行名が分かっても、支店名や口座番号が不明な場合、残高証明書を請求することで、故人の口座の有無と残高を把握できます。
| 請求先 | 請求方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行 | 故人の氏名・生年月日を伝え、全支店調査を依頼 | 死亡したことの証明(戸籍謄本など)と、相続人であることを証明する書類が必要です。 |
| ゆうちょ銀行 | 貯金事務センターへ問い合わせ | ゆうちょ銀行は特に利用者が多いため、最優先で確認しましょう。 |
都市銀行や地方銀行はそれぞれ手続きが必要ですが、過去に取引の心当たりのある銀行から優先的に連絡しましょう。手数料(1口座あたり1,000円〜数千円)がかかることが一般的です。
ステップ③ 証券会社や保険会社も調べる
預金だけでなく、株式や投資信託、生命保険も忘れてはいけません。
証券会社: 故人の名前で届いている「特定口座年間取引報告書」を探しましょう。
保険会社: 「保険証券」や「払込証明書」を確認します。生命保険金は、相続税の非課税枠が適用できる場合があるため、特に重要です。
一度の問い合わせで契約の有無を確認できる「生命保険契約照会制度」というものもあります。
これは、法定相続人や遺言執行人などが保険加入状況を照会できる制度で、申請の際は、照会者の本人確認書類や相続関係を証明する戸籍などが必要です。
詳細はこちら(一般社団法人生命保険協会)のホームページをご覧ください。
故人の預金はいつから引き出せる?(口座凍結のルール)
故人の預金は、相続開始後すぐに引き出せるわけではありません。銀行が故人の死亡を知った時点で、その口座は「凍結」されます。
口座が凍結されるとできなくなること
入金、出金、振込、公共料金の引き落としなど、すべての取引ができなくなります。
預金を勝手に引き出すことはNGです。遺産分割前にお金を勝手に引き出すと、他の相続人との間でトラブルになるだけでなく、「単純承認(すべての財産と負債を相続すること)」をしたとみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
「仮払い制度」で一時的に引き出す
2019年の民法改正により、遺産分割前でも、一定の範囲内で預金を引き出せる「仮払い制度」が設けられました。これは、葬儀費用や当面の生活費など、緊急でお金が必要な相続人のために作られた制度です。
引き出し限度額:「口座残高 × 法定相続分 × 1/3」
※ただし、1つの金融機関につき150万円が上限
「急に現金が必要になった!」という場合は、この仮払い制度を利用して銀行窓口で手続きしましょう。ただし、この制度を利用して引き出した分も、後で正式な遺産分割の対象になります。
銀行での預金相続手続きの流れ(解約・名義変更)
預金の相続手続きは、遺言書の有無や相続人全員の合意状況によって、「解約」または「名義変更」のどちらかになります。
【相続手続きの主な流れ】
窓口で申出: 死亡の事実と相続の意向を銀行窓口に伝え、必要書類リストを受け取ります。
書類の収集: 必要な戸籍謄本や印鑑証明書などを集めます。
遺産分割方法の決定: 相続人全員で誰がどの預金を相続するかを決定します。(遺産分割協議)
必要書類の提出: 銀行にすべての書類を提出します。
解約・名義変更: 数週間後、指定した相続人の口座に資金が振り込まれるか、名義が変更されます。
解約手続きは、各金融機関ごとにすべて個別に行う必要があります。複数の銀行に口座がある場合、それぞれの銀行で必要書類を用意し、手続きを行う手間がかかります。
名義変更に必要な書類と注意点
名義変更に必要な5つの書類
銀行での手続きをスムーズに進めるために、あらかじめ揃えておくべき「5つの必須書類」と注意点を解説します。
| 種類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 本籍地のある役所 | 誰が法定相続人であるかを確定させるために必須。最も時間と手間がかかります。 |
| ② 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地のある役所 | 現在の相続人であることを証明します。 |
| ③ 相続人全員の印鑑証明書 | 住民登録している役所 | 遺産分割協議書に押印した実印の証明として必須。発行から3ヶ月以内などの制限がある場合あり。 |
| ④ 遺産分割協議書(または遺言書) | 相続人全員で作成 | 誰が何を相続するかを明記した書類。遺言書があればそれが優先されます。 |
| ⑤ 銀行所定の相続届 | 銀行窓口 | 銀行独自の書式です。全員の実印押印が必要です。 |
名義変更手続きに関する3つの注意点
戸籍謄本の収集が難しい:
故人の本籍地が転々としている場合、複数の役所に請求しなければなりません。最初の役所で「除籍謄本」を取得し、その前の本籍地をたどっていく作業が必要です。
全員の実印押印が必要:
遺産分割協議書や銀行の相続届には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。一人でも協力が得られないと手続きはストップします。
相続人が海外在住の場合:
印鑑証明書の代わりに、サイン証明書(拇印証明書)や宣誓供述書といった、現地の領事館や公証人役場で発行される特殊な書類が必要になります。
まとめ:最初の一歩は「調査」と「情報共有」
預金や金融資産の相続手続きは、一見複雑に見えますが、まずは「どこに」「どれだけ」の財産があるかを正確に調査し、その結果を相続人全員で共有することが成功の鍵です。
特に戸籍謄本の収集や、相続人全員の合意を得るプロセスは時間がかかります。迷ったり、忙しくて手が回らないと感じた場合は、早めに司法書士やファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談し、スムーズな手続きを目指してください。
関連記事