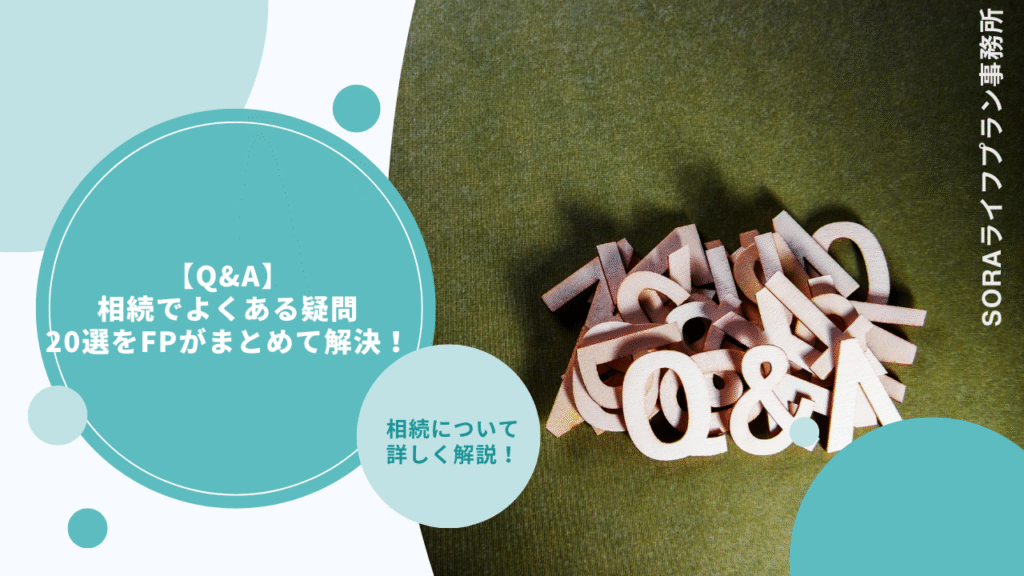
【Q&A】相続でよくある疑問20選をFPがまとめて解決!
相続手続きや税金の話は、「どこから手をつけていいか分からない」「専門用語が多くて不安」と感じる方が多いものです。特に家族が亡くなった直後は、時間との勝負になることもあります。
この記事では、ファイナンシャルプランナー(FP)が、相続に関するよくある質問20個を厳選し、Q&A形式で分かりやすく解説します。このページを読めば、あなたの抱える疑問が少しは解決すると思いますよ。
相続が始まったら最初にすべきこと(手続きの初動)
家族が亡くなったら、最初にすることは何ですか?
まずは落ち着いて、以下の3つのことを確認しましょう。
死亡届の提出:期限は死亡を知った日から7日以内です。
遺言書の有無の確認:遺言書があれば、原則としてその内容に従います。
財産の全体像の把握:プラス(預金、不動産)とマイナス(借金)をリストアップします。
遺言書が見つかりました。勝手に開けてもいいですか?
自筆証書遺言の場合、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。開封してしまうと、過料(罰則)の対象となる可能性があります。ただし、公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要です。
故人の銀行口座はすぐに凍結されるのですか?
銀行が故人の死亡を知った時点(家族からの連絡や新聞の訃報など)で、口座は凍結され、原則として入出金ができなくなります。生活費が必要な場合は、事前に葬儀費用などを引き出しておくか、「仮払い制度」の利用を検討しましょう。
遺言書の有効性に関する質問
遺言書に「日付」の記載がありません。有効ですか?
いいえ、無効になります。自筆証書遺言は、「全文の自筆」「日付の自筆」「氏名の自筆」「押印」の4つの要件をすべて満たさなければなりません。日付は非常に重要な要件です。
遺言書で「法定相続分を無視した分け方」をしてもいいですか?
はい、遺言書の内容は法定相続分に優先します。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の相続分を請求する権利があります。極端に不公平な分け方をすると、後で「遺留分侵害額請求」で揉める原因になります。
遺言書に書いてある内容と、相続人全員の意見が食い違ったら?
原則は遺言書の内容に従いますが、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割することも可能です。その場合は、その旨を記した「遺産分割協議書」を作成します。
相続手続きの期限に関する疑問
相続放棄の期限はいつまでですか?
故人の死亡(または自分が相続人であることを知った日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続税の申告期限はいつまでですか?
故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに申告・納税しないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
不動産の名義変更(相続登記)にも期限はありますか?
2024年4月1日から義務化されました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。早めの対応が必要です。
準確定申告(故人の所得税申告)の期限は?
故人が事業をしていたなど、生前に所得があった場合、相続人が故人の代わりに所得税の申告と納税を行う必要があり、期限は相続開始から4ヶ月以内です。
よくある相続税の疑問
そもそも相続税は誰でもかかるのですか?
いいえ。相続財産の合計額が「基礎控除額」を超えない限り、相続税はかかりません。多くの人は基礎控除額以下で、申告の必要がないケースが多いです。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
死亡保険金には税金がかからないと聞きましたが?
生命保険金は、非課税枠があります。
非課税枠の計算式: 500万円 × 法定相続人の数
この非課税枠内で収まる場合は、相続税はかかりません。非課税枠を超える部分は課税対象になります。
相続税の特例で一番大きいものは何ですか?
「配偶者の税額軽減」です。配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額までは税金がかかりません。この特例を使うことで、多くの場合、配偶者の相続税はゼロになります。
マイホームを相続した場合、相続税の負担を軽くできますか?
はい、「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。これは、一定の要件を満たす自宅の土地について、評価額を最大80%減額できる非常に大きな特例です。ただし、適用には相続税申告が必要です。
相続で揉めないための心得と実務
相続で一番揉める原因は何ですか?
一番の原因は、「不動産」と「感情的なしこり」です。
不動産:公平に分けにくく、評価額をめぐって対立しやすい。
感情:生前の介護や貢献度、兄弟間の不公平感が、遺産分割協議で爆発することが多いです。
遺産分割協議書は、なぜ必ず必要なのですか?
遺産分割協議書は、相続人全員の合意の証拠となる書類です。銀行口座の解約や不動産の登記など、後のすべての手続きで必要になるパスポートのようなものです。
相続財産がマイナスだった場合、相続放棄以外に選択肢はありますか?
「限定承認」という方法があります。これは「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する」というものです。手続きが複雑ですが、「どうしても残したい財産があるが、借金も怖い」という場合に有効です。
疎遠な相続人がいる場合、どうやって話し合いを進めますか?
疎遠であっても、その人抜きで遺産分割協議を進めることはできません。まずは内容証明郵便などで正式に連絡を取り、話し合いの場を設定する必要があります。それでも難しい場合は、弁護士に依頼して交渉を代行してもらうのが確実です。
自分の介護をしてくれた長男に多く財産をあげたいのですが?
それを実現するために遺言書を書きましょう。遺言書で「全財産を長男に」と指定できます。遺言書がない場合、介護の貢献は「寄与分」として認められますが、その立証は非常に難しくなります。
相続手続きに不安があります。誰に相談すればいいですか?
相談内容によってプロを使い分けましょう。
全体像の把握、ライフプラン:ファイナンシャルプランナー(FP)
相続税の計算、節税対策:税理士
不動産の登記、相続放棄:司法書士
揉め事の仲裁、交渉:弁護士
相続人調査、遺産分割協議書など書類の作成:行政書士
まとめ:不安を解消してスムーズな相続へ
相続は人生で何度もない大きなイベントであり、不安や疑問が生じるのは当然です。
しかし、「期限がある手続きを把握すること」と「事前に遺言書などで対策をしておくこと」の2つを行うだけで、不安の大部分は解消されます。
このQ&Aを参考に、必要に応じて専門家を上手に活用し、家族間の「争族」を未然に防ぎ、スムーズで円満な相続を実現しましょう。
