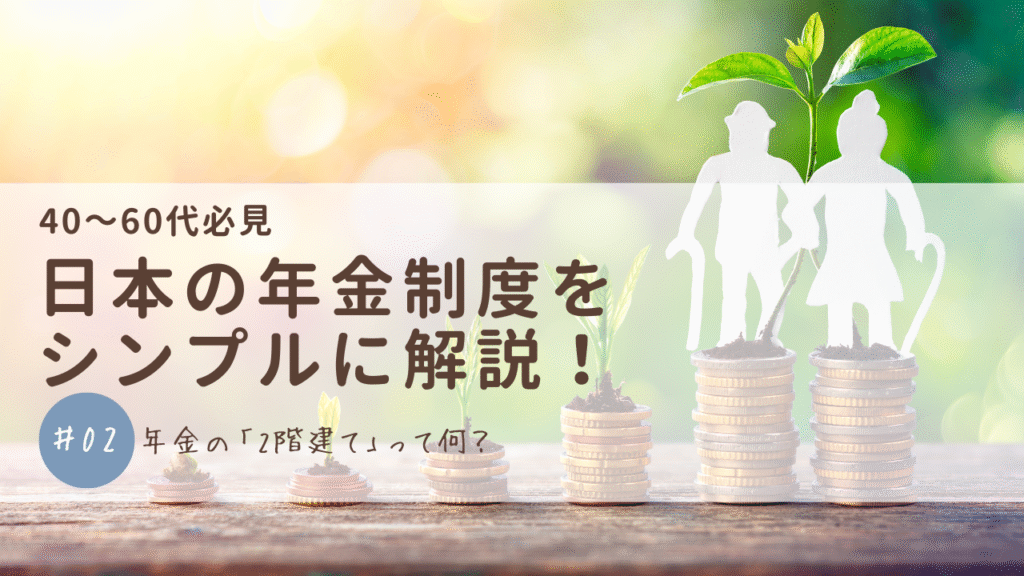
【図表でわかる】日本の年金制度をシンプルに解説!年金の「2階建て」って何?
あなたの人生設計を支える「年金」という名の建物
年金という言葉を聞くと、複雑で難しそう、あるいは「将来は本当にもらえるの?」といった漠然とした不安を感じる方も多いでしょう。しかし、日本の年金制度は、実は私たちの生活を守るために綿密に設計された、非常に理にかなった「建物」のようなものです。この建物の構造と、その賢い使い方を知ることで、年金制度をうまく活用し、最適なタイミングで受け取ることができるようになります。
本記事では、年金制度の基本である「2階建て」の構造から、将来の年金額を増やす方法、そして自分の年金がいくらになるのかを調べる具体的な方法までを、図や表を使いながら誰にでも分かりやすく解説します。この解説を通して、年金という制度が単なる「貯金」や「支払い」ではなく、より安心できる未来を築くための重要なライフプランツールであることが理解していただけると思います。
年金の2階建てって何?「国民年金」と「厚生年金」の違いを徹底解剖
日本の公的年金制度は、すべての国民が共通で加入する「1階部分」と、会社員や公務員が上乗せで加入する「2階部分」の「2階建て」構造になっています 。さらに、個人や企業が任意で加入する「3階部分」も加わることで、あなたの老後を支える強固な「3階建て」の建物が完成します 。

1階部分:国民年金(基礎年金)
この1階部分は、すべての国民に共通する「土台」です。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することが義務付けられています 。国民年金は、最低限の生活を保障する役割を担っており、保険料は原則として全員が同じ金額を納付します 。
この制度の加入者は、職業によって以下の3つの区分に分かれています。
- 第1号被保険者
自営業者、フリーランス、学生、無職の人などです 。国民年金のみに加入しており、自分で保険料を納める必要があります 。 - 第2号被保険者
会社員や公務員など、事業所に雇用されている人です 。厚生年金に加入しており、国民年金保険料は厚生年金保険料に含まれているため、別途納める必要はありません 。 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者です 。20歳以上60歳未満で、年収などの要件を満たしている人が該当します。この区分に該当する人は、国民年金保険料を自分で納付する必要がありません 。
2階部分:厚生年金
2階部分は、1階部分の国民年金に上乗せして加入する制度です。会社員や公務員など、事業所に雇用される人が加入します 。厚生年金に加入している人は、老後には国民年金(基礎年金)に加えて厚生年金(老齢厚生年金)も受け取ることができます 。
国民年金が原則定額の保険料であるのに対し、厚生年金の保険料は「給与や賞与の額」に応じて決まる点が大きな特徴です 。保険料は労使折半(被保険者と勤務先が半分ずつ負担)で、給与から天引きされるため、個人で納付する必要はありません 。老後に受け取る年金額も、現役時代の給料と加入期間に応じて変動します 。
3階部分:私的年金
年金制度は、公的年金の「2階建て」に加えて、個人の努力で積み上げる「3階部分」を持つことができます 。これは、企業が任意で設立する「企業年金」や、個人が任意で加入できる「iDeCo(イデコ)」、「国民年金基金」などが該当します 。これらの私的年金は、公的年金に上乗せして受け取ることができ、より豊かな老後生活を築くための「屋根裏部屋」のような役割を果たします。
図解で比較:国民年金と厚生年金の決定的な違い
多くの人が抱く「結局何が違うの?」という疑問に、以下にまとめた図表でお答えします。
| 項目 | 国民年金 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 加入対象者 | 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人 | 会社員、公務員など事業所に雇用される人 |
| 保険料の納付 | 第1号被保険者:自身で納付 第2・3号被保険者:納付不要 | 労使折半 (本人と勤務先が半分ずつ負担)で、給与から天引き |
| 保険料の算定基準 | 原則定額 | 所得に応じて定率 (給与と賞与の18.3%を労使で折半) |
| 老後の年金受給額 | 定額の老齢基礎年金 | 老齢基礎年金 + 所得に応じた老齢厚生年金 |
年金制度は「所得再分配」の仕組み
国民年金と厚生年金は、表面的な違いは加入対象者や保険料にありますが、その本質的な違いは「所得再分配」という機能にあります 。国民年金は、収入の多寡にかかわらず、すべての国民に一律で最低限の生活を保障する「セーフティネット」の役割を担っています 。
一方、厚生年金は収入に比例して保険料を納めるため、現役時代に高所得だった人ほど多くの保険料を負担し、老後に受け取る年金額は高くなります 。しかし、国民年金(基礎年金)が所得の多寡にかかわらず定額であるため、高所得だった人ほど多くの年金を受け取れるとはいえ、現役時代ほどの所得格差は生じないようになっています 。
このように、年金制度は単なる「個人の貯金箱」ではなく、社会全体でリスクを分かち合い、所得を間接的に分配することで助け合う「社会保険」の仕組みなのです 。この仕組みを理解することは、なぜ年金が「社会全体で支え合う」必要があるのかという、制度の根幹を理解することにつながります。
年金はいつからもらえる?受給開始年齢の今とこれから
公的年金は原則65歳から受け取ることができますが、これは「常にそうだった」わけではなく、また「今後もそうである」とは限りません。時代の変化に合わせて、年金の受給開始年齢も変わり続けています。
現在の仕組み
現在、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに、原則として65歳から受け取りが始まります 。ただし、過去には一部の老齢厚生年金が60歳から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」という制度がありました。これは、厚生年金に一定期間加入した人が、本来の年金受給開始年齢である65歳になるまで受け取れる年金です 。この特別支給の年金の受給開始年齢は、男性は2025年度、女性は2030年度までに、段階的に65歳に引き上げられます 。
将来の展望:さらなる引き上げはあるのか?
日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料で高齢者を支える「賦課方式」が基本です。しかし、日本は世界に類を見ないスピードで少子高齢化が進んでおり、高齢者が増え、現役世代が減ることで、この仕組みを維持することが難しくなっています 。この財政的な課題を解決するためには、年金支給開始年齢のさらなる引き上げが議論されています 。
すでに、国際的な動向を見ると、米国では67歳、英国では68歳、ドイツでは67歳まで年金の支給開始年齢を引き上げることが予定されています 。日本でも、年金財政の安定化を目指し、将来的に67歳への引き上げを検討すべきという議論が活発に行われています 。
年金制度は「働ける年齢」の延長と不可分である
年金の支給開始年齢の引き上げは、単に国が決める数字ではありません。これは社会全体の「高齢者雇用」と密接に関わっています 。もし受給開始年齢が65歳から67歳に引き上げられる場合、その間の2年間を無収入で過ごすわけにはいきません。年金制度を維持するためには、高齢者が継続して働ける社会環境を整備することが前提となります 。
このことから、年金問題はもはや単なる「お金」の問題ではなく、労働市場や社会システム全体の問題であることがわかります。個人としても、65歳以降も働き続けられるスキルやキャリアを築くことが、年金制度の変動リスクに対応する最大の防御策となります。年金は国任せにするものではなく、自分で管理し、育てるべき資産であるという意識を持つことが、未来の安心につながるのです。
老後のお金が最大84%増!年金の「繰り下げ受給」を賢く使う
年金は原則65歳から受け取ることができますが、「受け取りを遅らせる」ことで年金額を大きく増やすことができる制度があります。これが「繰り下げ受給」です。2022年の法改正により、その効果はさらに大きくなりました 。
繰り下げ受給の基本
繰り下げ受給とは、65歳からの年金受給をあえて遅らせることで、年金額を増やす制度です 。年金を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、この増額率は一生涯変わりません 。
2022年4月の法改正により、受給開始年齢の上限が従来の70歳から75歳に延長されました 。これにより、最大で84%も年金額を増やすことが可能になりました。(0.7% × 12ヶ月 × 10年 = 84%)
メリット・デメリットの徹底比較
最大84%増という言葉だけを聞くと非常に魅力的ですが、もちろん注意すべき点もあります。メリットとデメリットをしっかりと理解することが、賢い選択の第一歩です。
・年金受給額が一生涯増える
増額された年金額は、長生きするほど総受給額が増えるため、長寿リスクに備える有効な手段となります 。
・確実な運用
株式投資などと異なり、元本割れのリスクがなく、確実な増額が保証されている点が大きな魅力です 。
・税金・保険料の負担増
年金額が増えれば、それに伴って所得税・住民税や社会保険料(国民健康保険料、介護保険料など)も増えます 。その結果、手取り額は増額率ほどにはならない可能性があります 。
・加給年金が受け取れない可能性
65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金という扶養手当のような年金がもらえますが、繰り下げ期間中は支給されません 。また、加給年金は配偶者が65歳になると支給が終了するため、もらい損ねる可能性があります 。
・長生きできないと損をするリスク
繰り下げ期間中に早く亡くなった場合、受け取れる総額が減少する可能性があります 。
シミュレーション:損益分岐点は何歳?
繰り下げ受給の最大の懸念点である「何歳まで生きれば得をするか」を具体的な数字で見てみましょう。
| 受給開始年齢 | 年金月額(例) | 65歳からの受給累計額を上回る年齢 |
|---|---|---|
| 65歳 | 5.0万円 | |
| 70歳 | 7.1万円 (42%増) | 82歳頃 |
| 75歳 | 9.2万円 (84%増) | 87歳頃 |
※年金額は年間60万円(月額5万円)の場合の例です 。
このシミュレーションからわかるように、70歳まで繰り下げた場合、82歳頃まで長生きすれば、65歳から受け取った場合よりも総受給額が大きくなります 。
繰り下げ受給は「ライフプランの選択肢」である
繰り下げ受給は「得か損か」という単純な考えで語られるべきではありません。これは、高齢期の働き方や生活費の状況、そして健康状態や家族構成に応じて、個人が柔軟に選択できる「ツール」なのです。
例えば、65歳以降も働き続ける予定があり、生活費の心配がない人や、もともと年金額が少なく税金や社会保険料の負担が少ない自営業者・フリーランスの人は、繰り下げ受給のメリットを最大限に享受できます 。一方、繰り下げ期間中に十分な収入がない場合、老後の資金を切り崩して生活することになりますので、そのような場合は、繰り下げ受給の選択は避けるべきでしょう 。
おわりに:未来の自分に最高の贈り物をするために
本記事では、日本の年金制度を「建物」に例えて、その構造と賢い使い方を解説しました。ここで解説したポイントを改めて振り返ってみましょう。
- 日本の年金制度は、国民年金と厚生年金からなる「2階建て」の強固な土台で成り立っています。
- 受給開始年齢は今後も変動する可能性があるため、柔軟なライフプランを立てることが重要です。
- 「繰り下げ受給」は最大84%増という大きなメリットがある一方、デメリットも理解し、個別の状況に応じて賢く選択することが重要です。
年金は、あなたの老後の生活を支える最も確実な収入源です。この複雑な制度を「自分事」として捉え、小さな一歩を踏み出すことが、将来の安心へとつながります。今日、この記事を読んだあなたが、未来の自分に最高の贈り物をするための第一歩を踏み出せることを願っています。
