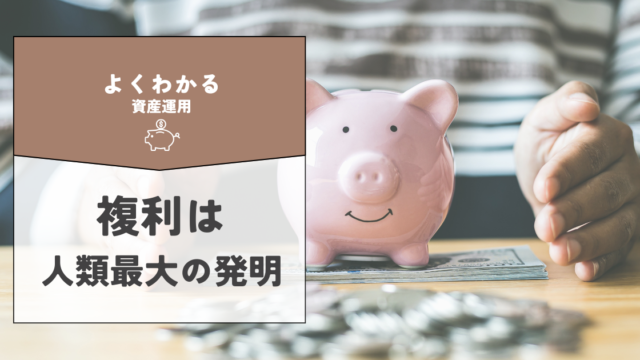FPがやさしく解説!iDeCo・つみたてNISAの基本ルールと選び方
お金のプロが勧める「老後資金づくり」の必勝法
「老後2,000万円問題」が話題になるなど、将来のお金に漠然とした不安を抱いている人は少なくありません。しかし、ただ闇雲に貯金するだけでは、インフレでお金の価値が目減りしてしまう時代です。そんな現代において、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)がこぞって勧めるのが、iDeCoとNISA(特に、つみたて投資枠)という二つの非課税制度の活用です。
これらの制度は、国が国民の資産形成を後押しするために用意した、いわば「特別な財布」です。この特別な財布の中で増やしたお金には、通常かかるはずの税金(運用益の約20%)が一切かかりません 。
本記事では、この二つの制度を「どっちが自分に合っているのか?」という視点から、その基本ルールから具体的な選び方、そして始める前に知っておくべき注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。
iDeCoとつみたてNISA、どっちが自分に合っている?
iDeCoとNISAは、どちらも資産を非課税で運用できるという共通点を持っていますが、その目的と特徴は大きく異なります。この違いを理解することが、自分に合った制度を選ぶための第一歩です。
| 項目 | iDeCo (個人型確定拠出年金) | NISA(新NISA) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 老後資金づくりに特化 | 老後資金に加え、住宅資金や教育費など幅広い目的 |
| 資金の引き出し | 原則60歳まで引き出し不可 | いつでも引き出し可能 |
| 税制優遇 | 運用益が非課税に加え、 掛金が全額所得控除 | 運用益が非課税 |
| 拠出上限 | 職業などにより上限あり | 年間360万円(つみたて120万円、成長240万円) 生涯で1,800万円 |
| 投資対象 | 金融機関ごとに異なるが、選択肢は少なめ | 幅広く、個別株投資も可能 |
【iDeCoが向いている人】
- 老後資金づくりに集中したい人
60歳まで資金を引き出せないため、「つい使ってしまう」という誘惑を断ち切り、確実に老後資金を積み上げられます。 - 所得税や住民税を軽減したい人
毎月の掛金が全額所得控除の対象となるため、拠出額に応じて税金の負担が軽くなるメリットがあります。年収が高い人ほど、この節税効果を大きく受けられます。
【NISAが向いている人】
- 資金の自由度を重視する人
いつでも資金を引き出せるため、将来の教育費や住宅購入資金など、老後以外のライフイベントにも備えたい人に適しています。 - 積立投資だけでなく、一括投資や個別株投資もしたい人
NISAは幅広い金融商品に対応しており、個別株への投資も可能です。株式投資に挑戦してみたい初心者や、非課税枠を効率的に活用したい経験者にも向いています。
結論として、資金に余裕があればiDeCoとNISAの両方を併用することが最も効果的な戦略です。しかし、どちらか一つを選ぶ場合は、「お金の目的」を明確にすることが重要です。
NISAをより理解したい方は下記の記事もご覧ください。
老後資金づくりに非課税制度を活用すべき理由
なぜ、iDeCoやNISAのような非課税制度を活用して資産を増やすことが、老後資金づくりにおいて不可欠なのでしょうか。その理由は、大きく二つあります。
理由①:運用益にかかる税金が「ゼロ」になる
私たちが投資で得た利益(運用益)には、通常、約20%の税金が課されます。例えば、運用益が100万円出た場合、約20万円が税金として引かれてしまいます。
しかし、iDeCoやNISAを活用すれば、この税金が一切かかりません。先ほどの例でいえば、20万円の税金がまるごと手元に残るのです。長期的に運用すればするほど、この非課税メリットは加速度的に大きくなります。
理由②:複利効果で雪だるま式に資産が増える
非課税制度の恩恵を最大限に享受するためには、「長期・積立・分散」という投資の王道が不可欠です。特に、非課税で得た利益を再投資に回すことで、「複利効果」が働きます。
複利とは、投資で得た利益が、次の投資元本に組み込まれていくことで、利息が利息を生む仕組みです。まるで雪だるまが坂道を転がりながら大きくなっていくように、資産が加速度的に増えていきます。
また、毎月定額を積み立てる「ドルコスト平均法」も有効です。これは、価格が安いときには多く、高いときには少なく自動的に購入することで、平均購入単価を抑える投資手法です。これにより、一時的に相場が下落しても「今は安くたくさん買えるチャンスだ」と冷静に考え、長期的な運用を続けやすくなります。
複利効果については下記の記事もご覧ください。
初心者でも失敗しない商品の選び方
iDeCoやNISAを始める上で、多くの人が不安に感じるのが「どの商品を選べばいいのか?」という点です。金融庁の基準を満たした商品の中から、自分に合ったものを見つけるためのポイントを3つご紹介します。
ポイント①:コスト(信託報酬)が安い商品を選ぶ
投資信託を保有している間、運用会社に支払う手数料のことを「信託報酬」といいます。このコストは、保有している限りずっとかかり続けるため、たとえわずかな差でも長期的に見れば大きな違いとなって現れます。同じような運用方針であれば、信託報酬がより安い商品を選ぶのが鉄則です。
ポイント②:自分の年齢やリスク許容度に応じて選ぶ
投資には元本割れのリスクがつきものです。老後資金を準備するにあたっては、このリスクを自分がどの程度許容できるかを考えることが重要です。
- 若年層(20~30代)
運用期間を長く確保できるため、多少のリスクを取ってでも大きなリターンを狙う、株式の割合が高いファンドを選ぶのも良いでしょう。 - 中年層(40代以降)
これまでの資産形成とこれからの老後を見据え、株式の割合を下げたり、債券などリスクの低い資産も一部取り入れたりするなど、バランスを重視した運用が選択肢になります。
ポイント③:元本確保型と投資信託を理解する
iDeCoには、元本が保証された「定期預金」などの商品(元本確保型)と、価格が変動する「投資信託」という商品があります。
- 元本確保型
元本割れのリスクがなく、安全性を重視する人に向いています。 - 投資信託
元本割れのリスクがある一方で、大きなリターンが期待できる商品です。
ご自身の運用目標やリスク許容度を把握した上で、どの商品を組み合わせるかを検討しましょう。
始める前に知っておくべき3つの注意点
iDeCoやNISAは、賢い資産形成の強力なツールですが、始める前に知っておくべき注意点もいくつかあります。
注意点① 無理のない金額を設定する
「おトクだから」と無理をして多額の掛金を設定してしまうと、後々の家計が苦しくなり、途中で続けられなくなるおそれがあります。特にiDeCoは、一度積み立てたお金は原則60歳まで引き出せないため、月5,000円からでも良いので、無理なく続けられる金額を設定することが何より重要です。
注意点② 金融機関選びを慎重に行う
iDeCoやNISAは、金融機関によって取り扱っている商品や手数料(口座管理手数料など)が異なります。特にiDeCoは、長く運用を続けるほど、わずかな手数料の差が大きな金額差につながります。
また、iDeCoの金融機関は年に1回変更できますが、手続きに手間がかかるため、できるだけ最初から納得のいく金融機関を選ぶことが大切です。取扱商品数やサービス内容なども比較検討しましょう。
注意点③ 投資は「自己責任」の原則を理解する
iDeCoやNISAを活用した資産運用は、元本保証ではありません。運用成果は市場環境によって変動するため、元本割れのリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。リスクをゼロにすることはできませんが、専門家であるFPに相談したり、資産運用について定期的に見直す時間を持ったりすることで、適切なリスク管理ができるようになります。
まとめ:今日から始める未来への投資
iDeCoやNISAは、単なる投資制度ではなく、自分自身の未来の選択肢を広げるためのツールです。老後の生活設計は、単なる「貯金」ではなく、「お金に働いてもらう」という発想で、非課税制度を賢く活用することから始まります。
まずは「家計の見える化」から始め、無理のない金額で、今日から一歩を踏み出してみましょう。その一歩が、将来の自分を大きく助けてくれるはずです。