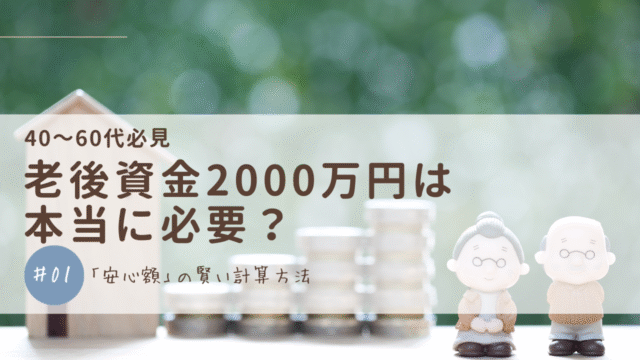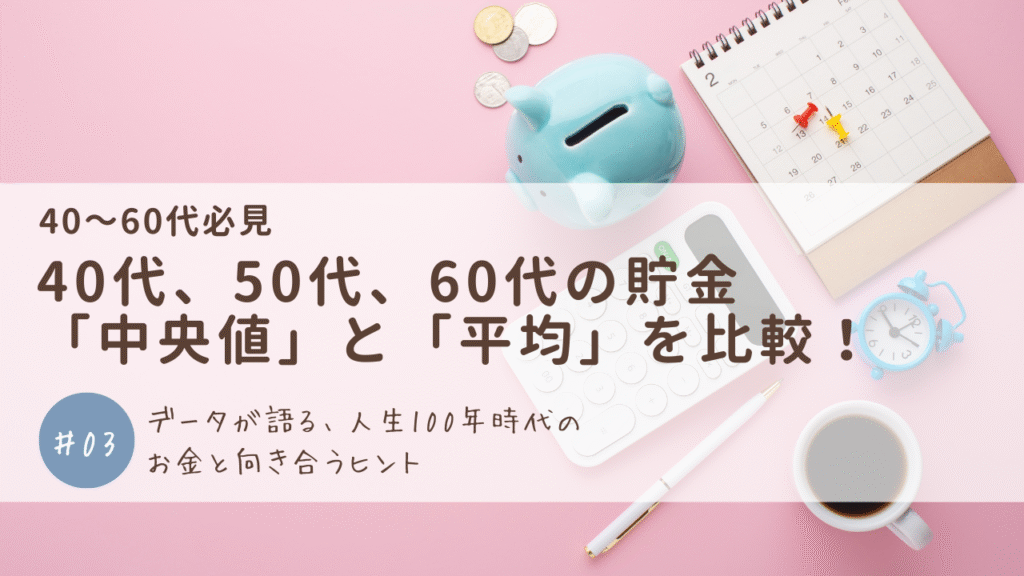
【年代別】40代、50代、60代の貯金「中央値」と「平均」を比較!
あなたの貯金、データで客観視してみませんか?
多くの人々が心の中で抱える「自分のお金は多いのか、少ないのか?」という漠然とした不安。友人や同僚の家計事情は、なかなか尋ねる機会がありません。この不安を解消し、自身の家計を客観的に捉えるための一つの有効な手段が、公的な調査データを参照することです。本稿では、金融広報中央委員会が実施した「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」の最新データをもとに、40代、50代、60代という人生の転換期における貯蓄の実態を詳細に分析します。
このデータを見る上で特に重要なのは、「平均値」と「中央値」という二つの指標を併せて理解することです。平均値は、一部の超富裕層や高額な貯蓄を持つ世帯によって大きく引き上げられる傾向があり、大多数の人々の現実的な状況を必ずしも反映しません。一方、中央値は、データを金額の低い順に並べたときにちょうど真ん中に位置する値であり、より多くの人々が実際に置かれている「現実」を映し出す鏡といえます。この記事では、この中央値に焦点を当て、各年代の家計が今どのステージにあるのか、そして次にどのような一歩を踏み出すべきかについて考察します。
あなたの貯金は多い?少ない?
ここでは、多くの人が関心を寄せる、年代別の貯蓄額をデータで具体的に示します。単に数字を並べるだけでなく、その数字の背景にある社会構造や家計の実情を深く掘り下げていきます。
家計の金融行動に関する世論調査によると、2人以上世帯における金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)は、平均値が1,374万円であるのに対し、中央値はわずか350万円でした。この平均値が中央値の約4倍にもなるという事実は、一部の世帯が平均値を大きく押し上げている現実を如実に示しています。これは、経済的な二極化、いわゆる「K字型の分断」が進行していることを示唆しているといえるでしょう。少数の人々が大きく資産を増やしている一方で、貯蓄がほとんどない、あるいは全くない世帯も一定数いるのです。
以下の表は、年代ごとの二人以上世帯と単身世帯の貯蓄額の「平均」と「中央値」をまとめたものです。この表を参照することで、自身の貯蓄額を客観的なデータと比較し、現状を正確に把握してみてください。
表:年代別・世帯構成別 貯蓄額の「平均」と「中央値」
| 年代 | 平均値(万円) | 中央値(万円) |
|---|---|---|
| 20代 | 384 | 84 |
| 30代 | 677 | 180 |
| 40代 | 944 | 250 |
| 50代 | 1,168 | 250 |
| 60代 | 2,033 | 650 |
| 70代 | 1,923 | 800 |
※家計の金融行動に関する世論調査(2024年)
この表が示すように、平均値と中央値の間には大きな乖離が見られます。この事実は、ごく一部の人が多額の資産を保有することで平均値を押し上げている一方で、多くの人が貯蓄の形成に苦戦している実態を物語っています。自身の貯蓄額が中央値に近い場合、それは特別なことではなく、多くの人々が同じような状況にあることを表します。この現実を理解することは、過度な不安を抱くことなく、現実的な目標設定へと意識を向ける第一歩となるでしょう。
40代に貯金が増えない理由
40代の貯蓄額は、他の年代に比べて伸びが緩やかに感じられるかもしれません。これは個人的な努力不足によるものではなく、人生のステージに起因する現象として捉えてください。この年代の家計を圧迫する主な要因は、「二つの大きな出費」です。
一つ目は住宅ローンという長期負債です。多くの家庭が40代でマイホームを購入し、高額な住宅ローンを組みます。注文住宅の平均借入金額は約3,500万円、分譲住宅では約3,000万円にもなります。この長期的な返済が毎月の家計を圧迫し、貯蓄に回せる金額が少なくなる大きな要因です。さらに、40歳から35年ローンを組むと、一般的な定年である65歳時点でも約1,000万円近い残債が残る可能性があり、老後まで返済が続くケースも珍しくありません。
二つ目は子どもの教育費です。子どもの教育費は、幼稚園から大学まで進学する学校の選択肢によって大きく変動します。文部科学省のデータに基づくと、すべて国公立の場合の総額は約800万円ですが、すべて私立の場合は約2,100万円もの費用がかかることがあります。特に高校から大学にかけての教育費は、40代から50代にかけてピークを迎えるため、この時期は収入が増えても、教育費の支出増が相殺し、貯蓄に回す余裕がなくなってしまうのです。
しかし、これらの出費は単なる「お金の流出」としてではなく、人生の「投資ステージ」として捉えてみてください。住宅ローンは、家という将来的な資産形成への投資であり、教育費は、子どもの未来と可能性への投資です。この時期は、貯蓄の停滞期であると同時に、将来の安定と豊かさの基盤を築くための「種まき」の時期なのです。そのため、無理に貯蓄額を増やすことを目指すのではなく、年間100万円程度の貯蓄を目安にしつつ、いかにキャッシュフローを安定させ、不測の事態に備えるかという「守り」の家計管理に重点を置くことが重要となります。
50代で急に増える人、増えない人の違い
50代は、家計状況が大きく変化する転換期です。40代の貯蓄停滞期を脱し、急速に貯蓄を増やす家庭がある一方で、思うように増えない家庭も存在します。この運命を分ける違いは、どこにあるのでしょうか。
貯蓄が急増する要因は、主に「子供の独立」と「退職金」の二つです。子どもが独立すると、これまで家計を圧迫していた食費や教育費が大幅に減少します。ある夫婦の事例では、子どもが独立したことで食費が月8万円から5万円に減り、家事に費やす時間も大幅に削減されたといいます。この時期は「第2の人生に向けた貯蓄のゴールデンタイム」といえるでしょう。また、50代後半から60代にかけて、勤続年数に応じた退職金を受け取る家庭が増えます。大企業などでは2,000万円を超えるケースも珍しくなく、この一時的な大きな収入が、貯蓄額を大きく引き上げる要因となります。
一方、貯蓄が思うように増えない家庭には、新たな出費や見落としがちなコストが発生しています。子どもが独立した解放感から、旅行や趣味などにお金を使いすぎてしまい、結果として貯蓄が増えないケースは少なくありません。また、子どもが扶養から外れることで、所得控除が減り、所得税や住民税が増えるという見落としがちなコストも発生します。さらに、50代は自身の老後資金準備と同時に、親の介護に直面する可能性が高まります。介護にかかる費用は、一時的な費用(平均47万円)に加え、月々の費用(平均9万円)が発生し、介護期間の平均が約5年と試算した場合、総額は在宅介護で約359万円、施設介護で約875万円にも上るといわれています。「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」
この年代で貯蓄を急増させるか、停滞させるかの違いは、子どもが独立すれば自動的に貯蓄が増えるという考えを持つのか、または積極的に家計の見直しを行おうとするのかどうかにかかっています。この時期はライフプランを見直す絶好の機会です。家計簿アプリなどを活用して家計の現状を正確に把握し、固定費(特に保険料)の見直しを行うことが、老後資金に向けた貯蓄を加速させる鍵となります。
老後資金は「貯める」から「増やす」へ
人生100年時代を豊かに生きるためには、これまでの「貯める」という守りの戦略に加え、これからは「増やす」という攻めの戦略が不可欠です。物価上昇や低金利の環境下では、ただ預貯金に現金を置いているだけでは、お金の実質的な価値が目減りしてしまうからです。
資産運用の重要性
インフレが進むとモノの値段が上がり、現金の価値が目減りします。このリスクに対抗するためには、物価に連動して価値が上がる傾向にある資産、例えば株式や不動産に投資することが有効です。
また、長年続いた低金利時代が終わり、金利が上昇する局面では、預金金利が上がるため、定期預金などの安全資産の魅力が向上します。
老後資金のための二つの柱:新NISAとiDeCo
老後資金の形成にあたっては、税制優遇制度を活用することが非常に効果的です。特に、新NISAとiDeCoは、その目的と特性を理解し、自身のライフプランに合わせて活用すべき二つの柱となります。
| 項目 | 新NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 運用益非課税 生涯投資枠1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) | 運用益非課税 掛金には上限あり |
| 資金の目的 | 老後資金に加え、教育費や住宅費など、幅広い目的 | 老後資金 |
| 資金の引き出し | いつでも引き出し可能 | 原則として60歳まで引き出し不可 |
| 税制優遇 | 運用益非課税 | 運用益非課税に加えて、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される |
新NISAとiDeCoは、それぞれ異なる強みを持っています。iDeCoは、その高い節税効果と60歳まで資金を引き出せない「強制力」により、着実に老後資金を積み上げたい人にとって非常に有力な選択肢です。一方、新NISAは、目的の柔軟性と資金をいつでも引き出せる利便性があり、教育費や住宅購入資金など、老後以外のライフイベントにも備えたい人に向いています。資金に余裕がある場合は、これら二つの制度を併用することが最も効果的な戦略となります。
【関連記事】
投資を始める際、多くの人はリスクを過大に捉えがちです。しかし、これからの時代、インフレリスクから資産を守るためには、預金だけに頼るだけではより大きなリスクを抱えてしまいます。そして投資は、特定の金融商品に一括で大金を投じるようなギャンブルではなく、「長期・積立・分散」という投資の王道を守ることで、時間を味方につけ、リスクを抑える「自己防衛」の戦略を考えるべきだと思います。年代別に投資戦略を変える必要もあり、60代以降の資産運用は、より安定したバランス型ファンドなどを中心に行うのがセオリーとなっています。また、退職金をすべて運用に回すのではなく、不測の事態に備えるための「予備費」として、目安1,000万円程度を確保しておきましょう。
おわりに:まずは一歩、家計の「見える化」から
老後資金は「2,000万円問題」に代表されるように、数字だけが先行して漠然とした不安を煽りがちです。しかし、大切なのは他人との比較ではなく、自身の現在地を正確に知り、未来に向けた具体的な計画を立てることです。
その第一歩として、まずはご自身の家計を「見える化」することから始めましょう。日本FP協会が提供する「家計の収支確認表」や「家計のキャッシュフロー表」といったオンラインツールを活用すれば、収入と支出のバランス、将来の貯蓄推移などを手軽に把握できます。今日の一歩が、漠然とした不安を安心に変え、明るく豊かな未来への扉を開く鍵となるはずです。